ここでは、台湾のお店でも使っているコーヒーの淹れ方のレシピをご紹介します。
ぶっちゃけレシピは、誰かの作ったものを真似るよりも、自分で探した方がいいものができます。
なぜなら人によって、下の2つが違うから。
①好みのコーヒーの味(酸っぱいのが好きだったり、苦いの、濃いのなど)
②コーヒーを淹れる環境(機械が違ったり、水やコーヒー豆が違えば最適なレシピは変わります)
なので、最高の家コーヒーのためには、ぜひご自分でオリジナルレシピを作って欲しいです。
ただ、いきなり0から作るのも大変ですし、基礎を抑えた方がレシピも作りやすいと思うので、
とりあえずここでは、参考として僕のレシピを紹介したいなと思います!
これを一度試してみて、後から微調整しながらお好みの味を見つけていってくださいね!
それでは、いきなりですがこれが私のレシピです。
後からちょっと触れますが、これは浅煎りのコーヒー豆のレシピなのでお気をつけください。
ただ、中煎りや深煎りもこれを少し調整するだけでできるので、見ておいても損はないですよ!
まずは、用意するものから行きましょう。
パスタの作り方を知ってても、フライパンがなければ作れませんからね。
準備するもの

- コーヒー豆:13g
- 熱湯:200ml
- ドリッパー(必須。V60だとamazonで300円ぐらいで買えます)
- コーヒー用ケトル(できれば欲しい。最悪やかんや計量カップでもできるけど、難しいです)
- スケール(あれば。タイマーまでついているとなおよし)
- グラインダー(手挽きでも機械でもOK。なければコーヒー屋さんで買うときに一緒に挽いてもらいましょう)
もしコーヒーの抽出器具を何も持っていない、という方もいると思います。
リーズナブルでおすすめの器具の紹介は下記をご覧ください!
(予定)リンク:ケトルのおすすめ
(予定)リンク:スケールのおすすめ
(予定)リンク:グラインダーのおすすめ
具体的な淹れ方
- ドリッパーを準備する
- お湯を沸かす
- コーヒー豆を挽く
- 最初に25-40gのお湯を注いで、蒸らす
- 大体25-30秒ごとに、残りのお湯を3回に分けて注ぐ
そんなに難しくはないです。上にある動画を見ながらだと、イメージが掴みやすいかと思います。
少しだけ、それぞれを細かく説明していきます。
ドリッパーを準備する

写真のように、ドリッパーに紙フィルターをセットします。
(下にガラスのおしゃれなやつを置いてますが、必須ではないです。直でマグカップでOK。)
紙をセットしたら、あらかじめお湯で紙を濡らしておくのがおすすめです。
湯通しする理由は、一つは紙の匂いを洗って取り除くため。
そしてもう一つは、コーヒーが冷めないようにカップや容器を温めるためですね。特に、プラスチックではなく陶器製のドリッパーを使用する場合は、お湯をたくさん注いで温めてください。ドリッパーが冷たいと、お湯を注いだときにお湯の温度が下がってしまい、うまく抽出されなくなってしまいます。
なおフィルターの違いについて知りたい方は、下記もチェックしてみてくださいね。
お湯を沸かす

お湯を沸かします。
私は基本、温度計とか使わずに熱湯をそのままケトルに入れて使います。
特に浅煎りのコーヒーは基本熱湯。もしそれより深い焙煎度の豆を使うときは、少しだけ温度が下がるのを待ってあげてもいいと思います。
(予定)リンク:熱湯でいいの?おすすめのお湯の温度と抽出の関係
コーヒー豆を挽く

13gの豆を中細挽きにします。(上の写真ぐらい)
スケールがない場合は、だいたいコーヒースプーン一杯弱ぐらいが13gになります。
あっさりしたのが好きな方は粗めに、逆に濃いのが好きな方は、豆の量を増やしたり、挽き目を細かくしてもOKです。
いきなり大胆に変えると味がものすごく変わるので注意してくださいね。
蒸らす

先に25-30gの少量のお湯を全体に満遍なく注ぎ、コーヒーになじませ、蒸らします。
(写真はスプーンで混ぜてますが、必須ではないです)
理由は、全部の豆に均等にお湯が触れるようにすることです。
いきなりドバッと注ぎ始めると、コーヒー粉の間からお湯がすり抜け、成分が抽出されないまま落ちてしまったり、一部のコーヒー粉にはお湯が過分に触れているのに、一部には触れていない、つまり過抽出、抽出不足の部分ができてしまい、味のバランスが崩れたりします。
人によってはさらに均一にするため、ここでスプーンで混ぜたりもします。私は最近、ドリッパー自体をぐるぐる回す派なのですが、お湯の注ぎ方を工夫して水流を作って混ぜたりと、色々なやり方があります。最初は特に気にしなくても大丈夫なので、全体にちゃんとお湯が触れるように、蒸らしを行ってください。
リンク:混ぜる?混ぜない?コーヒーの淹れ方の違い
残りのお湯を注ぐ

最初のお湯を注いでから、だいたい25-30秒ごとに、2-3回に分けて残りの水を注ぎ、最後はお湯が落ちきるまで待ちます。よく、落とし切る前に終わらせるって言っている人がいますが、全然気にしなくていいです。落ちるまで待ちましょう。
詳しくはこちらで説明しています。
(予定)リンク:お湯って落とし切らないほうがいいの?
注ぐ時のポイントは、中心に少し多めに注いであげることです。全体にきちんと満遍なく注ぐ必要があるので、層が厚くなっている中心部分に少し多めに、外側は気持ち少なめに注ぐのがポイントです。よく「のの字」と言われますが、中心から外、外から中心に円を描くように注ぐことで、バランスよくお湯を注ぐようにします。ケトルから出る水量が一定になるほど抽出も安定するので、少し練習してみてくださいね。ちなみに、縁側は注いではいけないと言う方がいますが、私の実感値ではあんまり気にしなくてもいいと思っています。
このやり方で注ぐと、だいたい1分40秒〜2分30秒で抽出が終わります。 3分以上かかるようなら、挽き目が細かすぎ、1分強で終わるようなら粗すぎです。参考にしてくださいね。
ちなみに、ゆっくり注いだり一回の注水量を減らすほど、抽出時間が伸びて、味が濃くなったりします。ここも本当に好みですね。
(予定)リンク:抽出時間とコーヒーの味の話
以上。コーヒーの淹れ方でした!
最初にも言いましたが、これはあくまで一例に過ぎず、それぞれの好みに合わせてレシピを作っていくのが大事だと思っています。もしこの先に興味がある方は、ぜひこちらのリンクをご覧いただき、自分なりのやり方を見つけてみてくださいね!
(予定)リンク:コーヒーレシピの作りかた
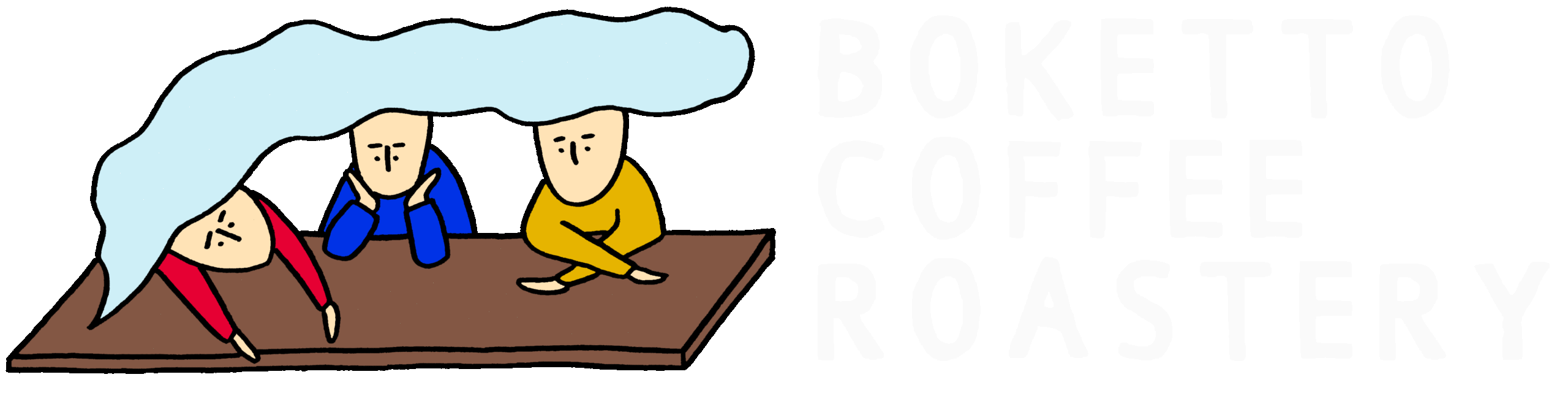





コメント